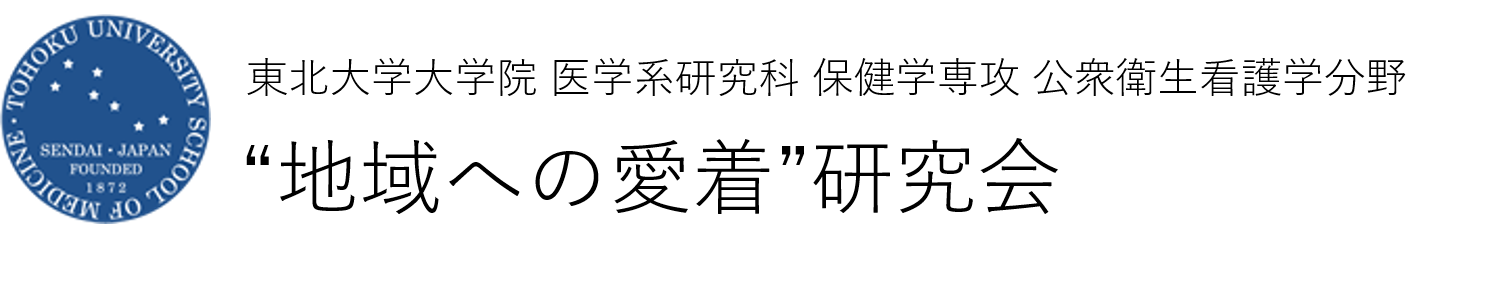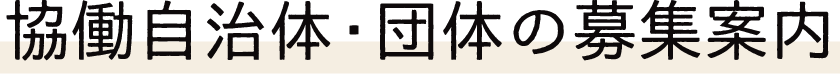TOP > 研究への参加をお考え・ご希望の方へ > 協働自治体・団体の募集案内
みなさんも自分の所属するコミュニティで一緒に地域の底力を高める
「地域への愛着メソッド」を共同実践してみませんか?
- 自分のコミュニティでも愛着を育むプログラムを実施したい
- プログラムに関心があり実施してみたいが、実施できるか不安である
- 自分のコミュニティでどのようなプログラムが実施できるか具体的な相談をしてみたい
など、興味や関心をお持ちになった方は、お気軽にお問い合わせください。
ともに地域への愛着を育み、健康を高め合っていきましょう!

「地域への愛着を育む健康増進プログラム」でのグループワークの様子
研究者・参加者の声
-
“地域への愛着”を公衆衛生看護活動の合言葉に!
生活者である私たち人間にとって、地域とは不思議なものです。問われてみないと意識しない、けれど、社会的な存在である人間にとって、地に足をつけて生きるために欠くことができないものです。問われれば、ここ、ここらへん、このあたり、このむら、このまち、というように、無意識のうちに自分もその地域の一部のように語り出すでしょう。自然や町並み、特産品や名所、家族や親戚、近隣所の人たちや友人といった人間関係網と一緒に、懐かしく楽しかった思い出や未解決の苦い思いや切ない気持が交錯し、希望と不安が表裏一体となって蘇ります。地域とは、人間の悲喜交々の営みによって織り成される公共の場であると同時に、一人ひとりの生活経験として個人の内面に五感を通じて蓄積され、自己の存在意味やアイデンティティと結びついていきます。住民の“地域への愛着”を育てること、それは未来の地域社会をデザインすることでもあります。QOL(いのち・くらし・人生の質)について探求する時、“地域への愛着”を合言葉にしていきたいと思います。主任研究者 大森 純子
(東北大学大学院 医学系研究科 公衆衛生看護学分野) -
ちょっとしたきっかけで、地域への愛着が育まれることを実感
私は平成26年に白井市桜台で開催された「地域への愛着を育む健康増進プログラム」に関わりました。
最初は、参加者の皆さんの表情は緊張気味だったのですが、徐々に和らぎ、プログラムの最後には、「桜台のことをあまり知らなかったけど、桜台のよいところが見つけられた」「こうやって知り合いができて、生活が楽しくなってきた」などの声が聞けるようになりました。
ちょっとしたきっかけで、地域への愛着が育まれ、その後の生活が楽しくなることを実感し、私も自分の住む地域でこのようなプログラムがあったら是非参加してみたいと思いました。共同研究者 田口 敦子
(東北大学大学院 医学系研究科 公衆衛生看護学分野) -
地域に愛着を抱くことが出来たら、人生の質に大きな変化をもたらしてくれる
“愛着”は日常的に当たり前のように、何かに対して抱いているものですが、この研究を通して、我々が生きていくうえで無くてはならない大事な概念であるとわかりました。そして、その一つに、自分たちが住んでいるまち、地域に愛着を抱くことが出来たら、人生の質に大きな変化をもたらしてくれることも確信できました。私自身も一人の人間として、健康や幸福を求めながら生きていくために、愛着あるコミュニティにおいて、他者とのつながりや相互作用を大事にしていきたいと思います。このような人生とリンクしながら関われる研究に出会えたことに感謝しています。共同研究者 三森 寧子
(聖路加国際大学大学院 看護学研究科) -
“地域への愛着”を感じることで、地域での生活が豊かになる
コミュニティの希薄化が指摘されるなか、共助の土壌やソーシャル・キャピタルの醸成をどのように創っていけば良いのかという課題は、きっと地域にかかわる多くの皆さんが抱えている想いだと思います。同じ生活基盤や社会資源、環境を共有する人々にとって、“地域への愛着”を感じられることにより、その地域での生活が豊かになるということは、生きる上でのとても大事な要素だと思います。
個人的には、近接コミュニティのなかでの緩やかな結びつきをどのように創り、維持できるかということに関心があります。ぜひ多くの方々と一緒に探究していきたいと思います。共同研究者 小林 真朝
(聖路加国際大学大学院 看護学研究科) -
地域への愛着は、自分を支え、人を助ける力に
自宅の周りの景色を見るとホッとするときがありませんか。あなたの住むまちを誇りに思うことはありますか。
四季の移り変わりを目にしたり、新しいお店ができたり、日々の楽しみは身近なところにあるかもしれませんね。
近所の人にあいさつしたり、まちの行事に参加したりすることで、人との交流が始まります。身近な人との関係は、いつか何かの時に大きな財産になることでしょう。
地域への愛着は、自分を支え、いつか人を助ける力になります。共同研究者 小野 若菜子
(聖路加国際大学大学院 看護学研究科) -
地域への愛着は、その人の内部を満たす温かで力強いエネルギー
この研究会に参加させていただいて、これまでに様々な出会いや学びの機会をいただきました。
その一例として、九州・沖縄地方の離島にインタビュー調査に行ったことを思い出します。私が訪れた日は、南国のイメージとは全く異なる、冷たい雨が降る日でした。インタビューの相手は、島内で店を営む老婦人です。インタビューが終盤に差し掛かったころ、老婦人は窓の外を眺めて深いため息をつきました。訳を聞くと、雨が長く続くと島内で土木業に従事する若者たちの仕事ができなくなってしまい、ただでさえ多くない給料が減ってしまうことを考えるととても悲しいと言うのです。我が事のように地域で暮らす若者のことを思う老婦人の姿から、とても深い愛を感じました。
“地域への愛着”は、特定の土地への執着などではなく、その人の内部を満たす温かで力強いエネルギーなのかもしれません。これからもこの研究会を通じて、新たな出会いや学びを得ていけることがとても楽しみです。共同研究者 酒井 太一
(順天堂大学 保健看護学部 公衆衛生看護学) -
自然の厳しさや生活の不便さも愛着の一部であることを学ぶ
地域への愛着の研究に関わり、多くのことを学んでいます。地域に対する人々の様々な思いは、人々の日常の生活に必要なスパイスであること、健康的な日々の質を高めることなど、専門職としての学びにとどまりません。
日常の中で私自身も人として生まれてきて、いつかは日常の中で最期を迎える。その日常が存在するのが地域での暮らし。その暮らしを誰かと共有できたり、懐かしんだりする日々を過ごすことが重要であることをこの研究を通して教えられました。自然の厳しさや生活の不便さも愛着の一部であることを研究で学び、ますます地域への愛着に関心が深まりました。今後の研究では、何が学べるのだろうとワクワクしています。共同研究者 宮崎 紀枝
(佐久大学 看護学部) -
プログラムに参加することで交流が生まれ、地域の良さを発見
私たちは、地域の愛着について、全国で活動されておられる方々をインタビューし、先行研究をレビューし、地域の愛着概念を生成してきました。地域の愛着概念をもとに、実証研究を行い地域の愛着が醸し出されるプログラム開発とアウトカム研究をしてきました。地域の愛着を測定する尺度も同時に開発を進めてきています。
今まで住んでいる地域にあまりリンクしていなかった参加者の方々が、地域の愛着プログラムに参加することで、同じ地域の参加者と親しくなり交流しあっています。
「私たちの地域ってこんな良いところあるのね!」と地域の良さを発見し、「何かこの地域のためにしてみたいなあ!」と心が動いてきた方々もおられます。
「一生住んでいく地域に愛着が持てたら、なんて素敵なことでしょう!」とキラキラと輝く目で語ってくださった参加者のお話に胸が熱くなりました。共同研究者 安齋 ひとみ
(目白大学 看護学部看護学科) -
地域への愛着は、生きる力
地域での看護や研究活動をしながら、これまで、たくさんの住民の方々とお会いする機会がありました。その中で、地域のことを思い、ご尽力されている方と出会い、お話しをさせていただいたり、共に活動させていただいたりしながら、この方のこの原動力は何だろうと考えていました。研究会に参加させていただき、改めて「地域への愛着」という概念から、これまで出会った方々を思い出すと、とても納得のいく答えが得られました。
研究会での学びをこれからも深め、広めていきたいと考えております。共同研究者 高橋 和子
(宮城大学看護学部)(平成26年度まで) -
「愛着」の概念は、ソーシャル・キャピタルの基盤となり得る重要なキーワード
平成27年度から参加させていただきました。私はソーシャル・キャピタルを研究のキーワードの1つとしています。
特に、地域や保健活動の現場において、ソーシャル・キャピタルが醸成されるメカニズムに興味を持っており、「愛着」の概念は、その基盤となり得る重要なキーワードになると考えております。
本研究プロジェクトの強みは、多方面の専門家が参加しながら、「愛着」について詳細な概念分析をしたうえで、介入研究によってその変化を検証し、さらにその妥当性の検証も視野に入れた研究設計を持っているところだと思います。
本研究によって、概念的にも、定量的にも、地域における「愛着」の重要性が提起できるように、微力ながら貢献していきたいと考えております。共同研究者 今村 晴彦
(東邦大学医学部 社会医学講座衛生学分野)(平成27年度から) -
「この地区が前より好きになった」
共同研究の実施地区は、高齢化率が14.5%(2013年)と市内一低いながらも、50~60歳代の割合が一番多い地区でした。日頃の訪問でも不在で共稼ぎ家庭が多いと予測され、地区内での交流ニーズは低い可能性がありました。そのため、プログラムでは「交流」を前面に押し出さず、参加する中で自然と交流できる内容や工夫を検討しました。しかし、開始当初、参加動機に交流を望む内容が多く、驚かされました。また、終了時には「この地区が前より好きになった」と話し、その後の自主的な集まりでは「地区で何ができるのか」と話すようになりました。今回の機会を通じて、身近な地区における交流のニーズは持っているが、あと一押しの場や機会を必要としている方々がいること、参加し交流を図る中で地区に対する考えや感じ方が変わっていくことを実感しました。松岡、戸田、篠田、矢野、平井、山田、三笠
(白井市)